こんにちは、あかい@編入です!
大学編入を目指す上で、「編入生は入学後、単位取得が大変…」なんて話を聞いたことはありませんか?
他大学に編入すると元の大学で取得した単位がどうなってしまうのか、在籍大学でどのくらい単位を取っておくべきか、疑問を持つ方は多いと思います。
本記事では、2つの単位認定方式と、在籍大学で取るべき単位について解説しますね!
編入を目指すか迷っている方は必見です!
・そもそも大学編入って何
・何の勉強をすればいいの?
このような疑問をお持ちだったり、大学編入についてあまりよく理解できていなかったりする方はこちらの記事からご覧ください!
大学編入における「単位認定」とは
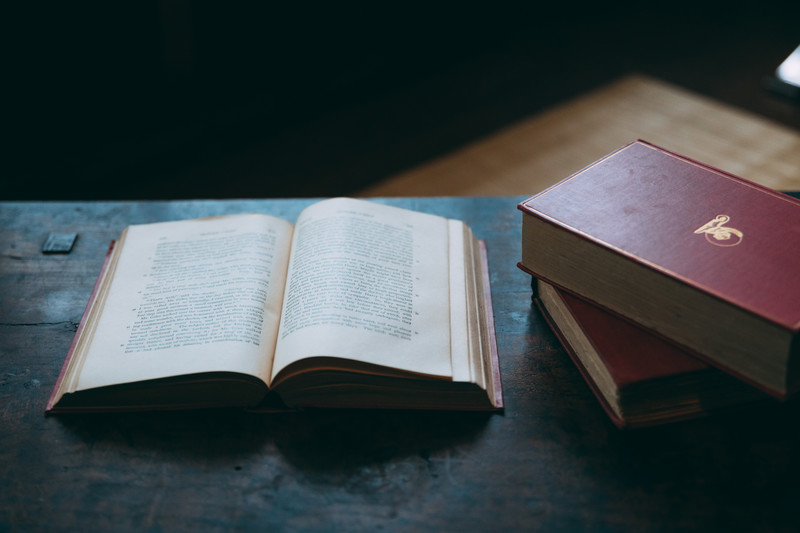
大学編入における単位認定とは、簡潔にまとめると次の通り。
編入前の大学で取得した単位を、編入後の大学の単位に組み入れること
前大学で取得した全ての単位が編入後の大学の単位に組み込まれるわけではなく、編入後の大学が認定単位の審査をして何単位分認定するか決定します。
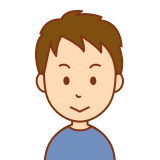
例えば、文学部→経済学部に編入したのに、履修していない経済学の必修単位まで認定されてしまっては編入の意味がないですからね!
認定される単位については同学部編入(法学部→法学部など)と他学部編入(法学部→経済学部など)で差が出ることが多々あり、同学部編入の方が多く単位が認められる傾向にあります。
編入後の単位認定制度は2種類
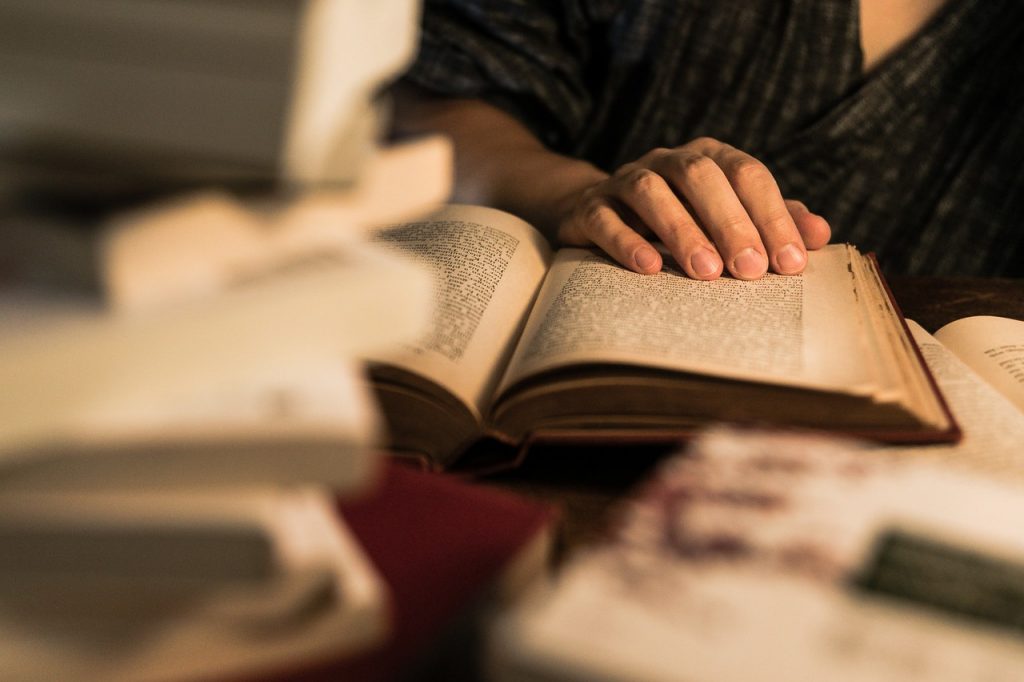
単位認定方法は大学ごとにまちまちですが、大きく2つの方法に分けられます。
ここでは便宜上、
・個別認定
・一括認定
以上2つの単位互換方式に分けて解説します!
個別認定
個別認定とは、在籍大学での既得単位をひとつひとつ認定するか検討していく方式です。
私が受験した大学のなかでは、上智大学がこの方式をとっています。
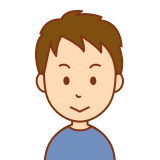
既得単位を個別に見ていくので、同学部に編入する方は認定されやすいです。
一方で、他学部受験の方は認定単位数が悲惨になることも…
他にも、北海道大学は個別認定の大学です。
一括認定
一括認定とは、一定の単位を一括で認定する方法です。
例えば、56単位一括認定の京都大学では、残りの68単位を二年間で取得する必要があります。
ここでは、専門科目か否かについて考慮せずに一括認定するので、1〜4年次までに取得すべき専門科目の単位を3〜4年の間に全て取得する必要があるんです。
神戸大学も60単位前後で認定してくれます。
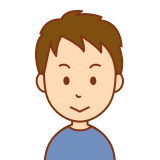
単位認定制度だけでなく、面接・志望理由書の有無や試験科目も異なります。
詳しくはまるわかり!大学編入データブックでチェック!
編入前に取っておくべき単位
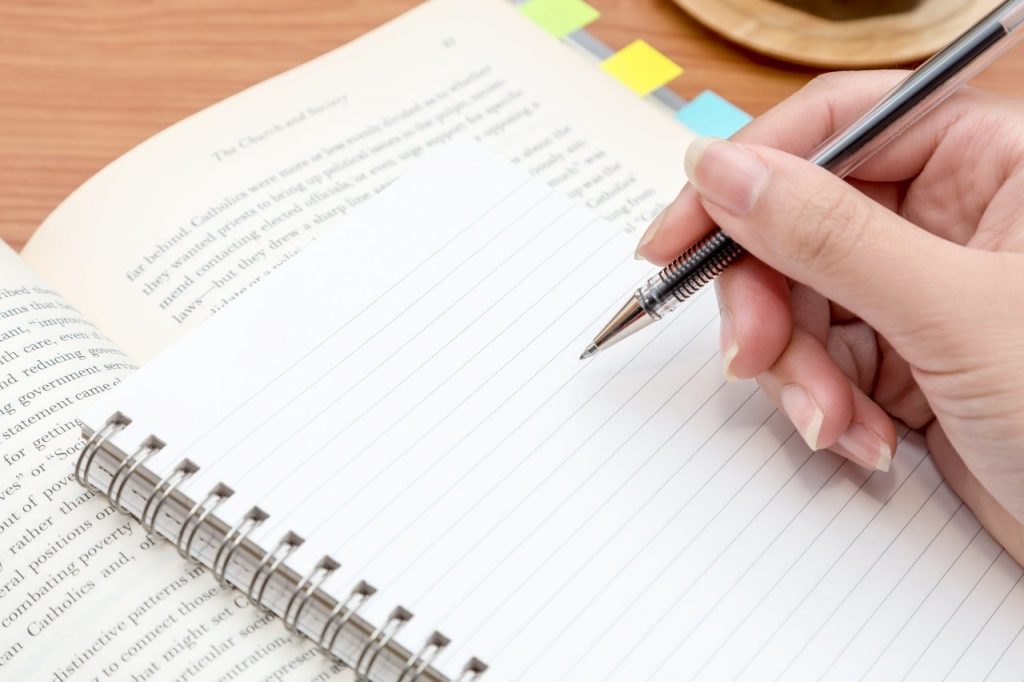
編入後の単位認定についてわかったと思います。
では、編入前の大学では何単位くらい取っておけばいいのでしょうか。
ここからは、在籍大学で取得しておくべき単位について解説します。
・出願基準単位
・編入後の専門科目単位
以上2つを意識して在籍大学では単位を取得するといいでしょう!
出願基準単位は絶対に取得すべき
出願基準単位は絶対に満たしましょう!
試験を受験できなくなってしまいます!
2年生後期までに60単位以上取得見込みを出願基準とする大学が多い印象ですね。
普通に単位を取得できて入れば、難なくクリアできるでしょう!
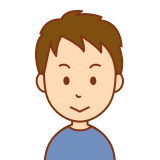
私が受験した大学だと、上智大学の出願基準は例外で結構厳しかったです。
2年生の前期までで60単位以上取得する必要があります!
編入後は専門科目の単位が認定されるかも
出願基準をクリアできそうであれば、編入後の専門科目の授業を取るのをおすすめします。
というのも、他学部への編入でも専門科目単位として認定してくれる場合があるからです。
専門科目の勉強にもなるので一石二鳥ですね♪
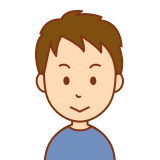
学部での授業も編入対策にかなり役立ちます!
事実、筆者が合格した大学の答案にも、ちょうど1〜2週間ほど前に在籍大学の授業で扱った内容をかなり盛り込みました!
編入後2年で卒業できる?

編入後の認定単位について、なんとなくわかったと思います。
ところで、編入すると認定単位がかなり減ることが多いのにお気づきでしょうか。
他学部を受験するとなおさらです。
話を具体的にするために、私のケースで考えてみましょう。
私は2年の後期までで88単位取得していました。
京都大学に編入した場合…88単位→56単位 = -32単位
神戸大学に編入した場合…88単位→60単位 = -28単位
京都大学、神戸大学に仮に編入する場合、1授業2単位とすると、それぞれ16、14の講義を余計に受講することになります。
卒業後の就職を目指す場合、大学3年生からインターンに参加して就活準備をする必要があります。
授業で大学3、4年生の貴重な時間を圧迫してしまう危険性があるといえますね…。
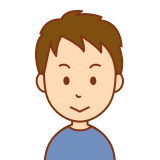
もちろん、優秀な先輩方は授業と就活を両立して、大企業に就職しています!
ただ、一般の学生と比べて留年の危険性が高いのも事実…
編入学にはメリットだけでなく、デメリットがあることもわかったと思います。
もっと編入学のメリット・デメリットについて知りたい方はこちら下記の記事へどうぞ
編入経験者の声
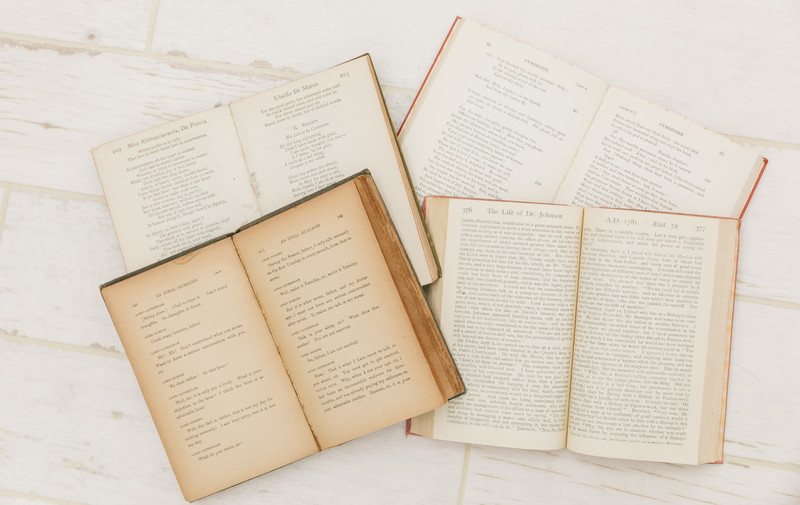
ここでは、Twitter上に挙げられている編入経験者の声をまとめておきます!
どのくらいの単位が認定されているか、参考にしてみてください!
神戸大学法学部
某大学法→神戸大法編入者が60単位を認定された旨のつぶやきを観測した。
— 講師N(法学編入)😺 (@hennyuugaku) May 26, 2021
他学部でも、法学や政治学関連の単位をとっておくと認定可能性がでてくるそう。
あと、神戸法学部の鬼単位を、前の大学の認定で潰すと編入ライフが快適になると聞いたことがある。
神戸大学法学部の単位認定では、法学系の授業の単位を専門科目単位として認定してくれます。
例えば、編入前の大学の「民法」の単位を取得しておけば、編入後の大学の「民法」の単位として認められ、編入後は必修科目であっても「民法」を履修する必要がなくなるというわけです。
北海道大学法学部
なんか今年の単位認定ホワイトすぎん?いつもこんな感じなんですかね。二年次編入で64単位認定なんてアルティメットパラダイスワールドでしょ。
— 🍮Oliviaの泉🍮 (@Aurelius2019) March 29, 2021
2年次編入にも関わらず64単位認定されたケースも。
法学部→法学部の編入ではありますが、ここまで単位が認められると編入後の生活がぐっと楽になりますね。
國學院大學法学部
数年前の編入経験者のお花見で、専門から編入して単位認定0の人いたけど、そろそろ卒業したのかな
— yu (@y_transfer_) March 31, 2021
専門学校から編入するとなんと認定単位が0なんてことも。
そうなると編入後2年での卒業は困難だと思われます…。
まとめ
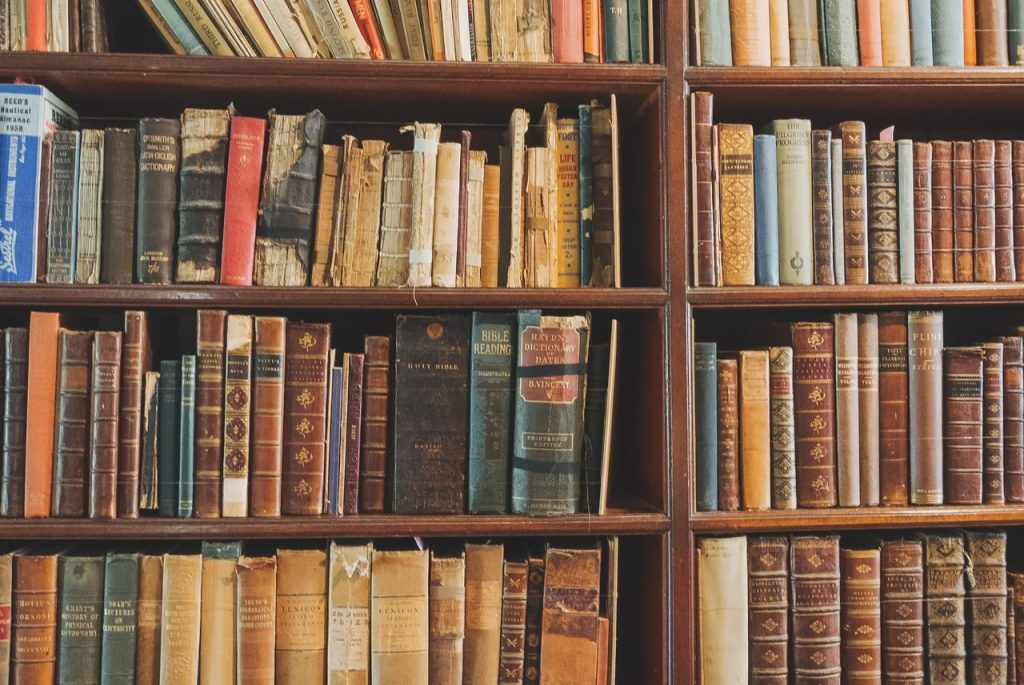
いかがだったでしょうか。
編入後の単位認定制度には、
・個別認定
・一括認定
以上2つの方法があります。
いずれにしても、編入後の単位は得てして少なくなってしまうものです。
それを十分踏まえて、皆さんは編入を目指してください。
「編入試験の勉強と同じくらい、編入後の大学でも勉強してる…」
なんて先輩もいるくらいですからね!
編入後まで見据えた将来設計をしてきましょう!
ちなみに、私は神戸大学法学部に合格しましたが、編入を辞退して在籍大学に残留するという選択をしました。その理由はこちらの記事で解説してます。
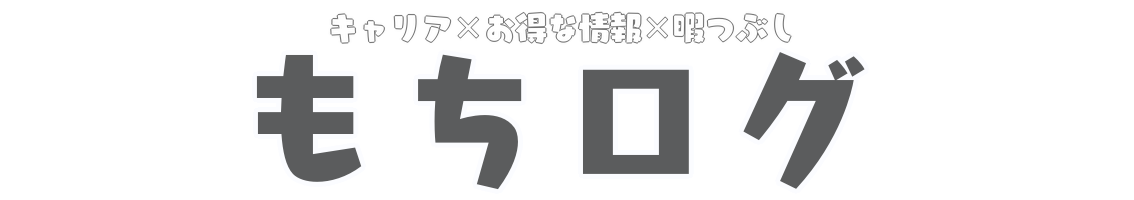
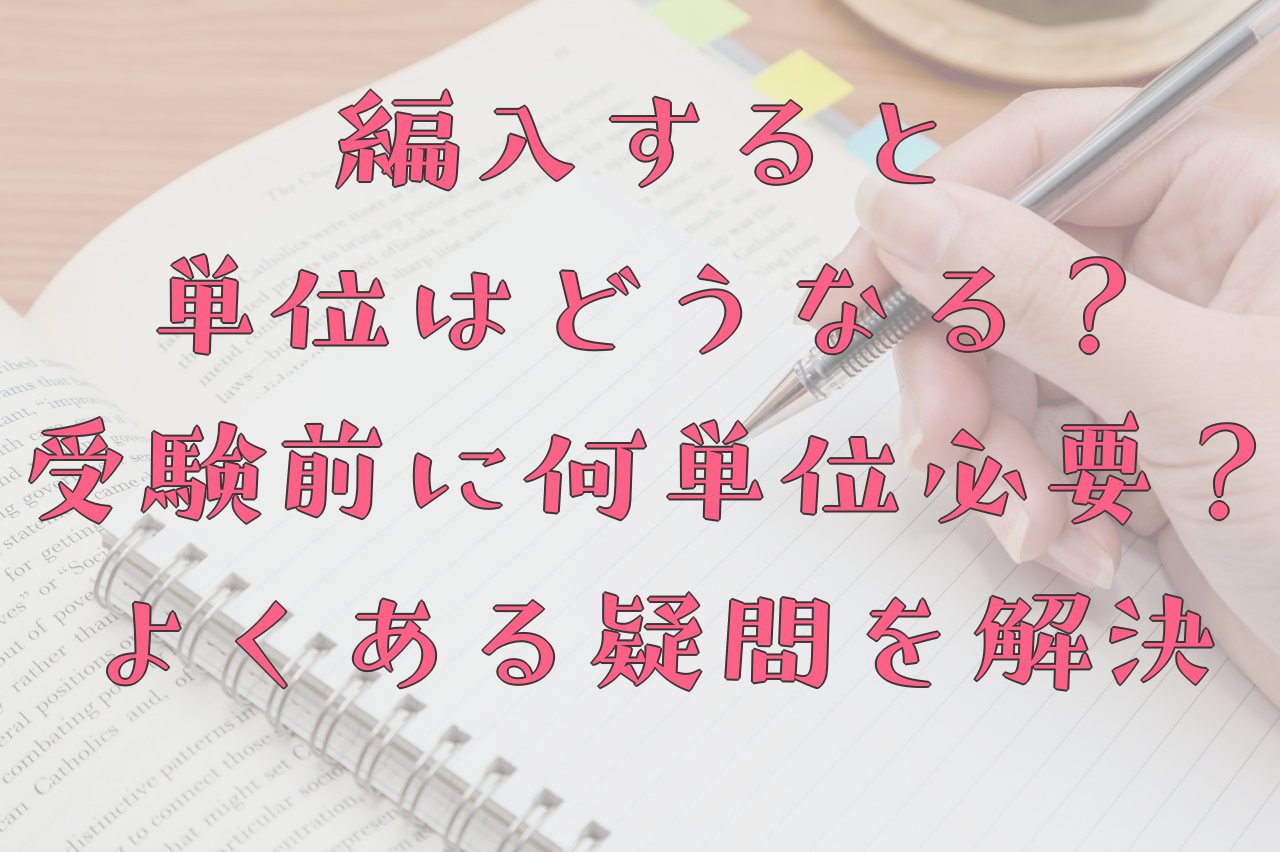
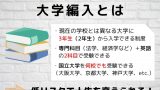




コメント